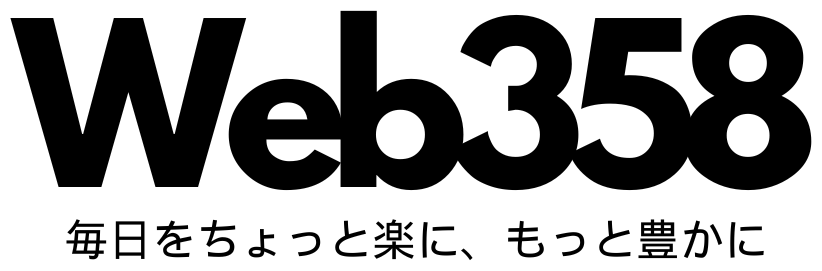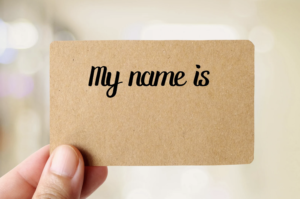「そろそろ学童を卒業させてもいいのかな?」
「小4になったら1人で留守番って…本当に大丈夫?」
子どもが小学生になると、保育園時代とは違った“放課後の壁”に直面します。
この記事では、共働き家庭に多い「学童保育をいつまで続けるべきか」の悩みに対して、
✅ 小4の壁とは何か?
✅ 一人留守番はいつから?
✅ 学童を卒業するか判断するポイント
をわかりやすく解説します!
目次
🏫 学童保育っていつまで通えるの?
多くの自治体では「小学3年生まで」が基本(公立の場合)
しかし、以下のような選択肢があります:
- 一部の公立学童は小6まで受け入れあり
- 民間学童や学習塾併設型なら小6まで通える施設も多数
- 条件により「延長利用」ができる自治体もあり(要確認)
📌 ポイント:地域や施設によって条件が違うので、早めに確認を!
🧱 「小4の壁」とは?
学童保育の受け入れが減るタイミング=子どもの放課後の選択肢が激減
さらに…
- 習い事の時間帯が合わなくなる
- 友だち同士の“遊び方”が変わってきて、放課後にポツン…
- 子どもが「もう学童イヤ」と言い出すタイミング
結果として、親が安心して働き続けにくくなる=“小4の壁”
🕒 留守番って何歳からできるの?判断の3ステップ
✔ 判断①:子どもの性格・タイプを観察
- 落ち着いている/一人遊びが好き → 比較的早くからOKな場合も
- 心配性・感情の起伏が激しい → もう少しサポートが必要かも
✔ 判断②:防犯・安全意識がどこまであるか
- インターホン対応は?
- 火元・コンセント・玄関の施錠などに注意が向く?
- トラブル時の行動(親に連絡など)ができる?
✔ 判断③:実際に「短時間の留守番」で練習してみる
- まずは30分から、徐々に時間をのばして反応をチェック
- 必ず連絡手段(スマホ or 固定電話)を確保しておく
📌 ポイント:「もう4年生だから」ではなく、“その子の準備”が何より大切!
🧠 学童卒業の前に検討したい代替プラン
- 放課後デイ(障害や発達支援が必要な場合)
- 民間学童 or プログラミング教室などの習い事系
- 祖父母との連携(送迎・留守番協力)
- 同級生の親と協力して“持ち回り”で見守るケースも
📌 まとめ:学童は「何年生まで」ではなく、「その子にとって必要か」で考える
子どもが自立に向かう時期はそれぞれ違います。
「周りがやめたから」「もう高学年だから」ではなく、
子どもの心と生活の安心のために、学童を“卒業”するタイミングを選びましょう。
親にとっても、働き方や生活を見直すきっかけになることも。焦らず、家族で話し合って進めることが大切です。