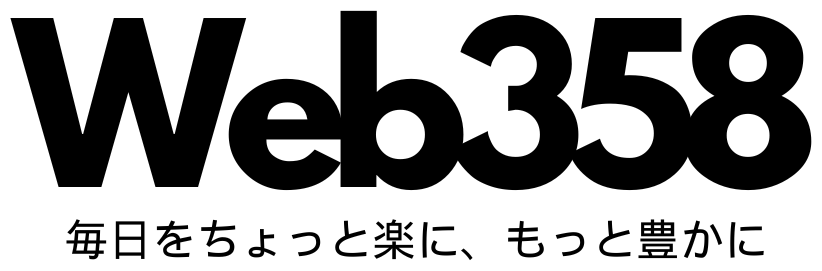日本の食卓で長く親しまれてきた味の素(うま味調味料)。
料理に旨みを加えるアイテムとして便利な一方で、「体に悪い」「害がある」といった声が根強くあります。
この記事では、味の素がなぜ「体に悪い」と言われるようになったのか、その背景と、科学的に実際どうなのかを中立的な立場から解説します。
味の素ってそもそも何?
味の素の主成分はグルタミン酸ナトリウム(MSG)。
グルタミン酸は昆布やトマト、チーズなどにも含まれる天然のうま味成分で、MSGはそれを精製した調味料です。
つまり「化学調味料」といっても、自然由来の成分を抽出して使いやすくしたものといえます。
「味の素は害」と言われるようになった背景
アメリカ発の“チャイニーズレストラン症候群”
1960年代、アメリカのある医学誌に「中華料理を食べた後に頭痛やしびれを感じた」という投稿が掲載されました。
このとき挙げられた原因のひとつがMSG(味の素)でした。
この話題がメディアで広まり、MSG=危険というイメージが拡散。
日本にもこのイメージが輸入され、「味の素は体に悪い」という印象が定着していったと考えられます。
“人工的なもの=悪”という風潮
1970年代以降、日本でも「無添加」「自然派」が好まれるようになりました。
この中で「化学調味料」は敬遠されるようになり、味の素もネガティブに扱われることが増えました。
科学的にはどうなの?味の素は本当に害があるのか
世界中の安全機関が「安全」と認めている
以下のような機関が、MSGの摂取について**「通常の食事レベルで健康被害はない」**と公式に発表しています。
- 世界保健機関(WHO)
- 国連食糧農業機関(FAO)
- アメリカ食品医薬品局(FDA)
- 欧州食品安全機関(EFSA)
つまり、正しい使い方をしていれば、健康に悪影響はないというのが科学的な共通見解です。
大量摂取には注意が必要
もちろん、何事も「過剰」はよくありません。
どんな調味料でも大量に摂れば体に負担がかかるように、MSGも大量に一気に摂取すれば胃腸に違和感を感じることがあるとされています。
ただし、それは“普通の食事ではまず起こらない”レベルの話です。
味の素=害、という誤解をどう受け止めるべきか?
私たちは「イメージ」や「口コミ」でモノを判断しがちですが、科学的な根拠に基づいた情報を知ることも大切です。
味の素は、うま味を補い料理の幅を広げてくれる調味料。
過度な心配をせず、適量・適切に使うことが健康的な食生活につながります。
まとめ:味の素は「使い方次第の便利アイテム」
- 味の素の主成分であるMSGは、多くの食品に含まれる自然由来のうま味成分
- 「害がある」とされた背景には、根拠の薄い噂や誤解が多い
- 科学的には、安全性が広く認められている
- 適量の使用であれば、健康リスクはほぼない
情報を鵜呑みにせず、自分で調べて判断することが大切です。
味の素をうまく取り入れて、毎日の食事をもっと豊かにしてみませんか?